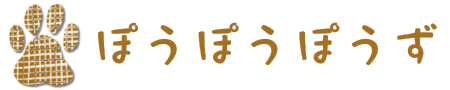この記事を読むとわかること
この記事を読むとわかること
• 特別天然記念物タンチョウの生態と絶滅危機から復活した歴史がすべてわかる
• 日本文化に深く根付いた鶴の意味と「鶴の恩返し」など民話の真実が理解できる
• 全国の観察スポットと最新の保護活動について詳しく知ることができる
タンチョウとは?日本の象徴的な鳥
特別天然記念物の美しき鶴
タンチョウ(丹頂、渡鶴、学名:Grus japonensis)は、日本を代表する大型の鶴です。
「丹頂鶴(タンチョウヅル)」「渡鶴(わたりづる)」とも呼ばれ、学名の「japonensis」は「日本の」という意味を持ち、英名でも「Japanese Crane(日本の鶴)」と呼ばれています。
1935年に天然記念物、1952年に特別天然記念物に指定され、日本の自然保護のシンボルとして大切に守られてきました。

なぜ「丹頂」というの?
成鳥の頭頂部には羽毛がなく、赤い皮膚が露出しています。この赤い頭頂を「丹(あか)」と表現したことから「丹頂(たんちょう)」と名付けられました。
基本データ

分類
- 目:ツル目
- 科:ツル科
- 属:ツル属
- 種:タンチョウ
別名
- 丹頂鶴(タンチョウヅル)
- 渡鶴(わたりづる)
- 英名:Japanese Crane / Red-crowned Crane
- 学名:Grus japonensis
身体的特徴
- 全長:約140cm(日本で見られる鳥類の中で最大級)
- 翼開長:約240cm(翼を広げた長さ)
- 体重:オス約10-12kg、メス約8-10kg
- 羽色:全身白色、風切羽と首は黒色
- 頭頂:成鳥は鮮やかな赤色(幼鳥は茶褐色)
- くちばし:黄緑色、先端は黄色
- 脚:黒色
寿命
- 野生:約20-30年
- 飼育下:平均約30年、最長記録は46歳6ヶ月
世界での生息状況
タンチョウは世界的に希少な鳥ですが、長年の手厚い保護活動により、その数は着実に回復傾向にあります。
特に日本(北海道)での生息数は増加が続いており、2024年度の調査(2025年3月発表)では過去最多となる1,927羽が確認されました。これにより、世界の総個体数も約3,800羽〜4,000羽ほどまで回復していると推測されます。
生息地域と個体数
- 日本(北海道):約1,900羽 留鳥として通年生息しています。1924年の再発見時にはわずか十数羽でしたが、100年の時を経て奇跡的な復活を遂げました。
- アムール川流域(ロシア・中国):約1,400羽 夏に繁殖し、冬は中国沿岸部や朝鮮半島へ渡ります。
かつては日本列島の広い地域(九州以北)に生息していましたが、現在日本で繁殖・定着しているのは主に北海道東部です。しかし近年では、個体数の増加に伴い生息域が徐々に拡大しつつあります。世界での生息状況
タンチョウの生態と生活史
四季折々の暮らし

タンチョウは季節によって生活場所を変える特徴があります。
春~夏(4月~9月):繁殖期
湿原の奥深くで繁殖活動を行います。つがいは縄張りを持ち、他のタンチョウが近づくと激しく威嚇します。
ヨシを直径約1mの大きさに積み上げて巣を作り、通常2個の卵を産みます。卵は鶏卵よりも大きく、長径約10cm、重さ約250gです。
オスとメスが交代で約30日間抱卵し、ヒナがふ化します。生まれたばかりのヒナは体長約13cm、体重約130gですが、成長速度が驚異的に速く、毎日約2cmずつ成長します。
わずか3ヶ月で体長約140cm、体重約10kgと、親とほぼ同じ大きさに成長します。

秋~冬(10月~3月):越冬期
家族単位で人里近くに移動し、給餌場や農地で過ごします。この時期、親は前年生まれの幼鳥と一緒に行動しています。
幼鳥の体には茶褐色の羽毛が残っており、「ピーピー」という幼い声で鳴きます。
2月以降になると、親鳥は次の繁殖に向けて幼鳥を突き放し始め、子別れが行われます。独り立ちした若鳥たちは群れで行動するようになります。
食性
タンチョウは雑食性で、季節や環境によって様々なものを食べます。
春~秋の食事
- 湿原:小魚、カエル、ザリガニ、昆虫類、貝類、植物の芽や実
- 干潟:小魚、カニ、エビ、ゴカイ、貝類
- 農地:昆虫類、ミミズ
冬の食事
- 凍結しない水辺の小魚や水生生物
- 給餌場のデントコーン(現在最も重要な餌)
冬季の自然採食地が減少したため、現在では人工給餌に大きく依存している状況です。
美しき求愛ダンス

タンチョウの最大の魅力の一つが、優雅な求愛ダンスです。
ダンスの動き:
- 翼を広げて飛び跳ねる
- 首を上下に振る
- くちばしで枝や草を投げ上げる
- お辞儀のような動作を繰り返す
- 2羽が向かい合って同時にダンス
このダンスは求愛だけでなく、つがいの絆を深めるという重要な役割も持っています。
タンチョウは一度つがいになると生涯同じ相手と過ごす「一夫一妻制」です。毎年春になると、つがいでダンスを踊り、絆を確認し合います。
6種類の鳴き声

タンチョウには用途の異なる6種類の鳴き声があります。
1. ユニゾンコール(同時鳴き)
オスが「コー」と鳴くと、メスが「カッカッ」と応えます。
意味:
- 周囲のタンチョウへの縄張り宣言
- つがいの絆を深めるため
2. フライトコール(飛行前の鳴き声)
「クォ、クォ、クォ…」と短く小さな声で鳴き合います。
意味:飛び立つ合図
家族全員が声を合わせると、首を斜め前に倒して走り出し、飛び立ちます。
3. コンタクトコール(連絡の鳴き声)
「コォーッ、コォーッ」と長くのばして鳴きます。
意味:離れた家族やグループを呼び合う
4. 警戒音
危険を感じたときに発する鋭い鳴き声です。
5. 幼鳥の鳴き声
「ピーピー」という高い声で親を呼びます。
6. 威嚇の声
縄張りに侵入者が来たとき、低く威圧的な声を出します。
強い縄張り意識
タンチョウは非常に縄張り意識が強い鳥です。
繁殖期には1つがいで数百ヘクタールもの広大な縄張りを持ち、他のタンチョウが近づくと激しく威嚇します。
威嚇の行動
- 頭の赤色部分が大きく広がる
- 首を伸ばして「ノッシノッシ」と歩いて近づく
- 鳴き合いで相手を牽制
- 飛び蹴りをくらわす
決着がつくまで延々と続くこともあります。
この強い縄張り意識のため、飼育下では1つのケージに1羽~2羽(ペア限定)、または1家族(3~4羽)しか飼育できません。
絶滅危機からの奇跡の復活 – タンチョウの歴史
江戸時代 – 手厚い保護の時代

江戸時代、タンチョウ(当時は「渡鶴」とも呼ばれた)は日本各地で見られ、将軍家によって手厚く保護されていました。
三河島の鶴御飼附場
江戸近郊の三河島村(現在の東京都荒川区荒川近辺)には、タンチョウの飛来地があり、江戸幕府が特別に保護していました。
保護の内容:
- 一帯を竹矢来で囲む
- 「鳥見名主」を設置
- 給餌係を配置
- 野犬を見張る「犬番」を常駐させる
- ささらを鳴らしてタンチョウを呼ぶ
- 近隣の根岸、金杉あたりでは凧揚げも禁止(鶴を驚かせないため)
タンチョウは毎年10月から3月にかけて見られ、午後6時頃から朝6時頃まではどこかへ飛び去り、その間は矢来内に入ることが許されていました。
タンチョウが来ないときは、給餌係が荒川の向こうや西新井方面にまで探しに行ったといいます。
鶴御成(つるおなり)
将軍が鷹狩によって鶴を捕らえる「鶴御成」という行事も行われていました。これは将軍の権威を示す重要な儀式でした。
明治時代 – 激減と絶滅の危機
明治時代に入ると、タンチョウの運命は急転します。
個体数激減の原因:
- 乱獲:銃の普及により、食用や羽毛目的で大量に捕獲された
- 湿原の開発:農地開拓により生息地が急速に失われた
- 森林伐採:土地の保水力が低下し、湧水が減少
これらの影響で、タンチョウはまたたく間に姿を消し、一時は絶滅したと考えられていました。
大正時代 – 奇跡の再発見
1924年(大正13年)、北海道釧路地方でわずか十数羽のタンチョウが再発見されました。
これは日本の自然保護史における奇跡的な出来事でした。人々はこのわずかな個体群を守るため、懸命な保護活動を開始します。
昭和時代 – 保護と復活
1935年(昭和10年):天然記念物に指定
1952年(昭和27年):特別天然記念物に格上げ指定
伊藤良孝氏の功績
鶴居村で酪農を営んでいた伊藤良孝氏は、1966年(昭和41年)よりタンチョウへの給餌を始めました。
厳しい冬、餌が不足するタンチョウのために、自費でトウモロコシを与え続けたのです。
その後、北海道から委嘱を受け:
- タンチョウ給餌人(1968年~1996年)
- タンチョウ監視人(1981年~2000年)
として、タンチョウ保護の最前線で活動しました。
冬季給餌の成功により、タンチョウの個体数は着実に増加していきます。
日本野鳥の会の活動
1987年、日本野鳥の会は北海道根室市でタンチョウが営巣する湿原約8haを買い上げ、民間としては初めての野鳥保護区を設置しました。
現在では24か所、約2,799.8haをタンチョウの生息地として保護しており、31つがいが生息しています。
現代 – 1,000羽超えの成功と新たな課題
現在、北海道東部には約1,650羽のタンチョウが生息しています。
絶滅寸前のわずか十数羽から1,000羽を超えるまで回復したことは、日本の野生動物保護の大成功例として世界的に評価されています。
しかし、新たな課題も浮上しています。
現在の課題:
- 給餌依存:冬の自然採食地が少なく、給餌に頼る状況
- 生息地の集中:一箇所に集中することで感染症リスクが高い
- 遺伝的多様性の低下:少数から増えたため遺伝的系統が少ない
- 交通事故:2024年度、過去最多の20羽が交通事故に遭遇
- 生息地の拡大:近年、道北地方でも繁殖が確認されている
日本文化におけるタンチョウ
縁起物としての鶴
タンチョウは古来より、最も縁起の良い鳥として日本文化に深く根付いています。
長寿の象徴
「鶴は千年、亀は万年」ということわざが示すように、鶴は長寿の象徴とされてきました。
実際のタンチョウの寿命は数十年程度ですが、その優雅な姿と白い羽色から、不老不死のイメージが重ねられました。
高貴の象徴
「鶴駕(かくが)」という言葉があります。これは皇太子の乗る車を指す言葉で、タンチョウが高貴の象徴とされていたことを示しています。
松竹梅と鶴
「松上の鶴」は、松、竹、梅と並ぶ縁起物の組み合わせとして有名です。
ただし、実際にはツル類は樹上には止まりません。この構図は、形態が似ているコウノトリと混同されていたという説と、縁起を重視した象徴的な表現だという説があります。
興味深いことに、江戸時代の博物誌『飼籠鳥』や『庶物類纂』では、「松上の鶴」の構図を実際にはありえないと否定または疑問視していました。
当時の人々は、鶴とコウノトリを区別しており、鶴が樹上に止まらないことも知っていたのです。
結婚式と鶴
現代の結婚式でも、鶴の意匠は欠かせません。
理由:
- 一夫一妻制で生涯同じ相手と過ごす
- 夫婦の絆の象徴
- 長寿と繁栄を願う
折り紙の鶴を千羽折った千羽鶴も、幸福と長寿を願う日本独自の文化です。
アイヌ文化とタンチョウ
北海道の先住民族アイヌの人々は、タンチョウを「サロルンカムイ」と呼びました。
これは「湿原の神」を意味します。
タンチョウは神聖な存在として崇められ、アイヌの伝承や儀式にも登場します。
和歌・俳句とタンチョウ
中村憲吉の歌
明治から昭和にかけて活躍したアララギ派の歌人、中村憲吉は、岡山後楽園を訪れた際、梅林を歩くタンチョウの美しい姿を歌に詠んでいます。
園内を自由に歩くタンチョウと梅の花が織りなす風景は、まさに日本美の極致でした。
中国・東アジアの鶴文化
道教と仙鶴
中国の道教では、タンチョウは仙人や仙道と深く結びついた聖なる鳥とされてきました。
寿星老人と仙鶴
寿星老人(南極老人星)が仙鶴に乗って飛来するという伝説があります。
この伝説は日本にも伝わり、長寿を祝う図柄として絵画や工芸品に描かれてきました。
太子晋の伝説
周の霊王の太子晋が仙人となり、白鶴に乗って去ったという説話も有名です。
このように、中国では鶴は仙界と現世を結ぶ神秘的な存在として描かれてきました。
瑞鳥(ずいちょう)としての鶴
タンチョウ(渡鶴)はその清楚な体色と気品のある体つきにより、特に神聖視され、瑞鳥(めでたいことの前兆となる鳥)とされました。
古来の中国や日本で単に「鶴」と言えば、通常はタンチョウを指していました。
中国古代美術の鶴
蓮鶴方壺(れんかくほうこ)
春秋戦国時代の青銅器「蓮鶴方壺」は、鶴と蓮をモチーフにした傑作です。
河南博物院や故宮博物院に所蔵されており、当時から鶴が高貴な存在として扱われていたことを示しています。
北宋・徽宗皇帝の「瑞鶴図」
1112年(政和2年)、北宋の皇帝・徽宗が描いた「瑞鶴図」は、中国絵画史に残る名作です。
ある日、皇宮の上に祥雲が生じ、群鶴が舞い、人々がこれを目撃したという瑞兆を記念して描かれました。
文人皇帝として知られる徽宗自身が絵を描き、詩を添えたこの作品は、鶴の神聖性を象徴する至宝です。
学名論争 – 中国の国鳥候補
興味深いエピソードがあります。
2007年、中華人民共和国国家林業局が、中国の国鳥にタンチョウの選定を提案しました。国務院も受け入れ、インターネットでのアンケートでは全510万票のうち65%を獲得という圧倒的な得票率でした。
しかし、タンチョウの学名「Grus japonensis」と英名「Japanese Crane」がともに「日本の鶴」を意味することから、後に議論を呼ぶこととなりました。
中国では古くからタンチョウが親しまれ愛されてきた歴史があるにもかかわらず、学名に「japonensis」という名がついているという状況です。
絵画・美術におけるタンチョウ
日本画での表現

タンチョウは日本画の重要なモチーフとして、数多くの名作に描かれてきました。
特徴的な描かれ方:
- 松と組み合わせた吉祥画
- 金箔を背景に優雅に舞う姿
- 雪景色の中での静謐な佇まい
- 夫婦で寄り添う姿(夫婦円満の象徴)
屏風絵
桃山時代から江戸時代にかけて、権力者の屏風絵に鶴が頻繁に描かれました。
狩野派や琳派の絵師たちが、金地に白い鶴を配した華やかな作品を残しています。
着物の文様
婚礼衣装や振袖に、鶴の文様は欠かせません。
代表的な文様:
- 飛鶴文(ひかくもん):空を飛ぶ鶴
- 舞鶴文(まいづるもん):ダンスを踊る鶴
- 鶴の丸文:円の中に鶴を配置
- 松竹梅に鶴:縁起物の組み合わせ
紅白の色使いと金糸の刺繍で、華やかに表現されます。
折り紙の鶴
日本を代表する折り紙作品が鶴です。
千羽鶴は、病気回復や世界平和を願う象徴として、現代でも広く作られています。
広島の原爆の子の像に捧げられる千羽鶴は、世界中から平和への祈りを集めています。
民話「鶴の恩返し」の世界

あらすじ
鶴との出会い
昔々、ある所に貧しいけれど心優しいおじいさんとおばあさんが住んでいました。
ある寒い冬の雪の日、おじいさんが町へ薪を売りに出かける途中、猟師の罠にかかって苦しむ一羽の鶴を見つけました。
「おお、おお、かわいそうに。今助けてやるからな」
おじいさんは鶴の罠をはずし、逃がしてやりました。
鶴はおじいさんの頭の上を三回まわり、「カウ、カウ、カウ」とさもうれしそうに鳴いて、山の方へ飛んでいきました。
美しい娘の訪問
その夜、激しい雪が降り積もりました。
おじいさんが鶴を助けた話をおばあさんにしていると、扉をたたく音がします。
戸を開けると、そこには美しい娘が立っていました。
「夜分すみません。雪で道に迷ってしまいました。一晩泊めていただけないでしょうか」
「ごらんの通り貧しい家ですが、よかったら泊まっていってください」
おじいさんとおばあさんは、娘を快く家に入れました。
娘との暮らし
次の日も、また次の日も雪は降り続き、娘は何日も家に留まりました。
娘は心優しく、炊事や洗濯など何でも甲斐甲斐しく世話をし、おじいさんとおばあさんを大いに喜ばせました。
ある日、娘はこう言いました。
「顔も知らない親戚のところへ行くより、いっそあなた方の娘にしてください」
子供のいない二人は、大喜びで承知しました。
機織りの約束
しばらくして、娘が言いました。
「美しい布を織りたいと思います。糸を買ってきていただけませんか?」
おじいさんはさっそく糸を買ってきました。
娘は部屋にこもる前、こう念を押しました。
「機を織っている間は、絶対に部屋をのぞかないでください」
そして部屋の戸を閉め、機織りを始めました。
カタン、カタン、カタン…
美しい布
三日三晩、機を織る音が響きました。
そして娘が部屋から出てくると、手には息をのむほど美しい布がありました。
白地に銀色が輝く、この世のものとは思えない美しさでした。
「これを町で売ってきてください」
おじいさんが町へ持っていくと、その布は高値で売れ、たくさんの食べ物とお金が手に入りました。
貧しかった二人の生活は、一変しました。
二度目、三度目の布
娘は「もう一度織ります」と言い、再び部屋にこもりました。
二度目の布も見事に売れました。
そして三度目…
娘はまた部屋にこもりましたが、今度は日に日にやつれていくように見えました。
約束を破る瞬間
心配になったおばあさんは、おじいさんに言いました。
「あの子、どうやってあんな美しい布を織っているのでしょう。とても気になります」
「だめだ。のぞかないと約束したじゃないか」
しかし、娘の様子が気になって仕方ありません。
ついに、おばあさんは好奇心に負けて、部屋の戸をそっと開けてしまいました。
正体の発覚
そこにあったのは…
娘の姿ではなく、一羽の鶴が自分の羽を抜いて、糸の間に織り込んでいる姿でした。
鶴の体からは、羽毛の大部分が抜かれ、痛々しい姿になっています。
驚いて立ちすくむおじいさんとおばあさん。
機織りを終えた鶴は、二人の前に現れて言いました。
「私は、あの時おじいさんに助けていただいた鶴です」
「ご恩を返すためにやってきました。このままずっとお二人の娘でいるつもりでした」
「でも…正体を見られてしまった以上、もうここにはいられません」
悲しい別れ
そう言うと、娘は鶴の姿に戻り、窓から飛び立っていきました。
「待っておくれ!」
「行かないでおくれ!」
おじいさんとおばあさんは引き止めようとしましたが、鶴は空高く舞い上がり、山の彼方へ消えていきました。
二度と、戻ってくることはありませんでした。
手元には、鶴が最後に織った美しい布だけが残されていました。
発祥の地 – 山形県南陽市
山形県南陽市漆山地区は、鶴の恩返し伝説の発祥の地として知られています。
同地に暮らしていた金蔵という人物の体験として伝承されており、以下の関連地名や史跡が現存しています:
- 鶴布山(かくふざん)珍蔵寺:鶴が織った布が宝物として納められたと伝わる
- 織機(おりはた)川:娘が機を織っていた場所にちなむ
- 鶴巻田:鶴が羽を休めた場所
- 夕鶴の里:語り部が民話を語り継ぐ施設(1993年開設)
資料館では、英語・韓国語・中国語(繁体字)の字幕付きでストーリー映像を視聴でき、海外からの観光客も訪れています。
地域ごとのバリエーション
鶴の恩返しは日本全国で報告されており、地域によって細かい違いがあります。
主なバリエーション:
- 老夫婦バージョン(一般的)
- おじいさんとおばあさんが鶴を助ける
- 娘として一緒に暮らす
- 鶴女房バージョン
- 若者が鶴を助ける
- 鶴は若者の妻となる
- 異類婚姻譚の要素が強い
- 子供ありバージョン
- 若者と鶴女房の間に子供が生まれる
- 子供を残して鶴は去る
- 羽毛織りバージョン
- 買ってきた糸ではなく、自分の羽毛で織る
- 日に日に痩せ細る描写がより生々しい
教訓と深い意味
鶴の恩返しには、いくつもの深い教訓が込められています。
1. 恩を忘れない心
鶴は命を救ってくれたおじいさんへの恩を忘れず、自分の身を削ってでも恩返しをしようとしました。
恩義を大切にする心の尊さを教えています。
2. 約束を守ることの大切さ
「絶対にのぞかないでください」という約束を破ったことで、幸せな関係は終わってしまいました。
どんなに親しい関係でも、約束は守らなければならないということを示しています。
3. 「見るなのタブー」の普遍性
世界中の民話に共通する「見るなのタブー」のモチーフです。
ギリシャ神話の「パンドラの箱」や「オルフェウスとエウリュディケ」、日本神話の「イザナギとイザナミ」など、禁忌を破ることで悲劇が起きる物語は数多くあります。
好奇心や疑心は時に大切なものを失わせるという普遍的な真理を伝えています。
4. 無理な関係は続かない
鶴は自分の身を削って布を織り続けました。しかし、自己犠牲による関係は長続きしません。
おじいさんとおばあさんが部屋をのぞかなかったとしても、いずれ鶴の命は危うくなっていたでしょう。
無理をしなければ維持できない関係は、結局お互いのためにならないという現代にも通じる教訓です。
5. 異類婚姻譚の意味
人間と人間以外の生き物が結ばれる「異類婚姻譚」は、日本独自の自然観を反映しています。
西洋では人間と動物の世界は明確に分けられていますが、日本では人間と自然が近い関係にあります。
鶴の恩返しは、「生きていくための原則」を語る物語でもあります。
この世には誰一人として同じ人間はいない。幸せに暮らしていくには、それぞれ異なる生き物同士、その違いを共有し、分かち合い、理解する必要がある。
鶴が繰り返し約束させた「見るなのタブー」は、まさにそのための約束だったのかもしれません。
木下順二「夕鶴」- 現代に蘇る鶴の物語

戯曲「夕鶴」の誕生
1949年(昭和24年)、劇作家木下順二が、鶴の恩返し伝説を基に戯曲「夕鶴」を発表しました。
原典は、柳田國男『全国昔話記録』第一編『佐渡昔話集』(1932年)中の「鶴女房」です。
「夕鶴」は木下順二の最高傑作と言われ、日本の現代演劇史に輝く名作として、今なお世界中で上演されています。
あらすじ
登場人物
- 与ひょう(よひょう):純朴な青年、炭焼き
- つう:与ひょうの妻、実は鶴
- 運ず(うんず):欲深い商人
- 惣ど(そうど):運ずの仲間
物語
雪深い村に住む純朴な青年・与ひょうは、傷ついた一羽の鶴を助けました。
ある日、つうという美しい娘が現れ、与ひょうの妻となります。
つうは「絶対にのぞかないで」と約束させ、部屋にこもって千羽織という美しい布を織ります。
その布を都で売ると大金になることを知った運ずと惣どは、与ひょうをそそのかし、つうにもっと布を織るよう強要させます。
お金にとりつかれた与ひょうは、つうに「もう一度織ってくれ」と頼みます。
つうは、お金で心を失った与ひょうに落胆しますが、千羽織を得ることで与ひょうの心が戻ってくることを信じて、布を織る決心をします。
しかし、与ひょうは約束を破り、布を織っているつうの姿をのぞいてしまいます。
そこには、鶴となって自分の羽を抜きながら布を織るつうの姿がありました。
翌日、すっかりやせ細ったつうは、千羽織を与ひょうに渡すと別れを告げ、空へ飛び立っていきます。
民話との違い
「夕鶴」は単なる恩返し物語ではなく、人間の欲望と純愛の葛藤を描いた作品です。
主要なテーマ:
- 金銭欲に翻弄される人間の弱さ
- 純粋な愛の尊さ
- 資本主義社会への批判
- 失ってから気づく大切なもの
与ひょうは悪人ではありません。しかし、周囲の欲望に流され、最も大切なものを見失ってしまう普通の人間です。
現代社会に生きる私たちも、与ひょうと同じ過ちを犯しているかもしれません。
オペラ「夕鶴」
1952年、作曲家 團伊玖磨(だんいくま)が「夕鶴」をオペラ化しました。
日本語によるオペラとして大成功を収め、日本オペラの最高傑作と評価されています。
つうのアリア「私を呼ぶ声が聞こえる」は、日本オペラ史上最も美しい曲の一つとされています。
海外でも「Yuzuru」のタイトルで上演され、世界中の人々に感動を与えています。
タンチョウ観察スポット完全ガイド
北海道 – タンチョウの聖地

鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ
住所:北海道阿寒郡鶴居村中雪裡南
運営:日本野鳥の会
特徴:
- 冬季給餌場として有名
- 11月から3月にかけて、最大200~300羽が集まる
- 観察センターあり、暖かい室内から観察可能
- レンジャーによる解説あり
見どころ:
- 早朝の飛来シーン
- 求愛ダンス(1月~3月)
- 家族の交流
- 給餌の瞬間
アクセス:
- JR釧路駅から車で約40分
- たんちょう釧路空港から車で約20分
ベストシーズン:1月~2月(最も多くのタンチョウが集まる)
阿寒国際ツルセンター「グルス」
住所:北海道釧路市阿寒町上阿寒23線40番地
特徴:
- 冬季給餌場と分館が併設
- タンチョウの生態を学べる展示
- 間近で観察できる
見どころ:
- ダイナミックな飛翔シーン
- つがいの絆を深める行動
- 幼鳥と親鳥の関係
アクセス:
- JR釧路駅から阿寒バスで約1時間
ベストシーズン:11月~3月
釧路市動物園
住所:北海道釧路市阿寒町下仁々志別11番
特徴:
- 北海道最大の動物園
- タンチョウの飼育展示あり
- 自然に近い環境での飼育
- 一年中観察可能
見どころ:
- 繁殖行動の観察
- ヒナの成長過程(春~夏)
- 間近での観察
アクセス:
- JR釧路駅からバスで約50分
開園時間:
- 夏季(4月~9月):9:30~16:30
- 冬季(10月~3月):10:00~15:30
音羽橋周辺
住所:北海道川上郡標茶町
特徴:
- 野生のタンチョウが自然採食する様子を観察
- 夏季の繁殖期にもタンチョウが見られる
- 運が良ければヒナ連れの家族に遭遇
アクセス:
- JR標茶駅から車で約15分
ベストシーズン:通年(冬季が観察しやすい)
岡山 – 西日本唯一の飛翔可能飼育

岡山後楽園
住所:岡山県岡山市北区後楽園1-5
特徴:
- 日本三名園の一つ
- 江戸時代からタンチョウを飼育
- 現在はケージ内での飼育
歴史:
- 1704年頃から飼育開始
- 戦後一時途絶えるも、1956年に中国から2羽を寄贈され再開
- 郭沫若(かくまつじゃく)氏の尽力
見どころ:
- 美しい庭園とタンチョウの調和
- 1~4月:繁殖羽で最も美しい時期
- 梅の花とタンチョウ
アクセス:
- JR岡山駅から路面電車で約25分
- 岡山ICから車で約20分
開園時間:
- 7:30~18:00(季節により変動)
入園料:
- 大人410円、子供140円
岡山県自然保護センター
住所:岡山県和気郡和気町田賀730
特徴:
- 北海道以外で唯一、飛翔可能な状態で飼育
- 30羽以上のタンチョウを飼育
- 広大な敷地で自然に近い環境
- 種の保存活動の拠点
見どころ:
- タンチョウの飛翔
- 求愛ダンス
- ヒナの子育て(春~夏)
- 四季折々の自然とタンチョウ
タンチョウが見られる季節:
- 春:求愛ダンス、抱卵
- 夏:緑豊かな環境、ヒナの成長
- 秋:紅葉の中のタンチョウ
- 冬:雪景色とタンチョウ
アクセス:
- JR和気駅からタクシーで約15分
- 山陽自動車道和気ICから車で約10分
開館時間:
- 9:00~16:30(月曜休館)
入館料:無料
観察のベストシーズン
冬季(11月~3月)
- 最もタンチョウを観察しやすい時期
- 給餌場に多数集まる
- 求愛ダンスが見られる(1月~3月)
- 雪景色とのコントラストが美しい
春季(4月~5月)
- 繁殖期
- つがいが湿原で営巣
- 観察は難しいが、運が良ければヒナを見られる
夏季(6月~8月)
- ヒナの成長期
- 家族で行動
- 比較的観察しにくい
秋季(9月~10月)
- 徐々に給餌場に集まり始める
- 家族連れが多い
観察のマナー
必ず守るべきこと:
- 給餌場以外では近づかない(100m以上離れる)
- 大声を出さない
- 追いかけない
- フラッシュ撮影禁止
- 車から降りて近づかない(道路横断中のタンチョウに注意)
- ゴミは必ず持ち帰る
- 餌を与えない(給餌場以外)
撮影のコツ:
- 早朝が最も美しい(朝日とタンチョウ)
- 望遠レンズ推奨(300mm以上)
- 三脚使用
- 忍耐強く待つ
保護活動の現状と未来への課題
日本野鳥の会の取り組み
野鳥保護区の設置
1987年以降、日本野鳥の会は北海道東部でタンチョウの生息地を買い取り、保護区化を進めてきました。
現在の保護区:
- 24か所
- 総面積:約2,799.8ha
- 生息つがい:31組
これは民間による野鳥保護区として日本最大規模です。
湿原の復元活動
鶴居村の早瀬野鳥保護区温根内では、周辺の森林開発により土砂が流れ込み、ヨシ原にハンノキが繁茂してしまいました。
1994年以降、タンチョウが繁殖できない環境になってしまったため、1999年からハンノキを伐採し、ヨシ原を復元する事業を開始しました。
その結果、2002年から再び繁殖が始まりました。
環境が悪化した場合には、それを復元する環境管理を継続的に行っています。
冬期自然採食地の造成
現在、タンチョウは冬の餌を給餌に大きく依存しています。
これを改善するため、冬も凍らない水路を作り、タンチョウが自然に餌を採れる環境を整備しています。
2009年、サンクチュアリ内に冬も凍らない水路を作り、樹木の間伐を行いました。
現在、最大20羽のタンチョウが冬に利用しています。
2014年までに、鶴居村内の農家の協力を得て、村内に15か所の自然採食地を造成しました。
環境省の取り組み
タンチョウ給餌に係る実施方針(2007年)
環境省は、給餌の適正化とタンチョウの自立を目指す方針を策定しました。
目標:
- 給餌への過度な依存からの脱却
- 生息地の分散
- 感染症リスクの低減
タンチョウ生息地分散行動計画(2013年)
一箇所に集中する現状を改善するため、生息地を分散させる計画を策定しました。
具体的な取り組み:
- 道東以外の地域での生息環境整備
- 道北地方での繁殖支援
- 新たな給餌場の設置
現在直面している課題
1. 交通事故の増加
2024年度、タンチョウの交通事故が過去最多の20羽に達しました。
環境省釧路自然環境事務所によると、2000~2024年度に傷ついたり死んだりして収容されたタンチョウ計806羽のうち、交通事故が原因だったのは約1/4の192羽にも上ります。
原因:
- 体が大きいため、すばやく飛び立てない
- 道路を横断する習性
- 車との距離感覚が不十分
対策:
- 釧路市動物園が事故防止を呼びかける動画を制作
- 「道路横断していたら必ず減速を」と啓発
- 注意喚起の看板設置
ドライバーの皆さんへ:タンチョウを見かけたら、必ず減速してください。
2. 給餌依存の問題

冬の自然採食地が不足しているため、現在も給餌に大きく依存しています。
問題点:
- 一箇所に集中することで感染症リスクが高まる
- 野生本来の行動パターンが失われる
- 給餌場周辺での環境負荷
解決策:
- 冬期自然採食地の拡大
- 給餌場所の分散
- 段階的な給餌量の削減
3. 遺伝的多様性の低下
現在の北海道のタンチョウは、わずか十数羽から増えた個体群です。
そのため、遺伝的な系統が少ないという問題があります。
遺伝的多様性が低いと:
- 病気への抵抗力が弱くなる
- 環境変化への適応力が低下する
- 繁殖力が低下する可能性
対策:
- 大陸個体群との遺伝子交流(慎重な検討が必要)
- 飼育下繁殖個体の遺伝管理
- 長期的なモニタリング
4. 生息地の集中リスク

現在、日本のタンチョウの大部分は北海道東部に集中しています。
一箇所に集中していると:
- 大規模な感染症が発生した場合、全滅のリスク
- 大規模災害(地震、火山噴火など)の影響を受けやすい
- 環境収容力の限界
対策:
- 道北地方での生息環境整備
- 本州への分散の検討(慎重な議論が必要)
- 岡山など飼育施設での保険個体群の維持
私たちにできること
1. 観察マナーを守る
- 適切な距離を保つ
- 静かに観察する
- 餌を与えない
2. 交通安全への協力
- タンチョウを見かけたら減速
- 道路横断中は停止して待つ
- クラクションを鳴らさない
3. 保護活動を支援する
- 日本野鳥の会への寄付
- ボランティア活動への参加
- 観察施設の利用(入館料が保護活動の資金になる)
4. 知識を広める
- タンチョウの現状を周囲に伝える
- SNSで正しい情報を発信
- 子どもたちへの環境教育
タンチョウ雑学・豆知識
尾羽の色の誤解
古い絵画では、タンチョウの尾が黒く描かれていることがよくあります。
しかし、実際の尾羽は白色です。
では、なぜ黒く見えるのでしょうか?
答え:長くて黒い風切羽(かざきりばね)が白い尾を覆っているため、立っているときは尾が黒いように見えるのです。
飛んでいるときや羽を広げたときには、白い尾羽がはっきりと見えます。
英名の由来
タンチョウの英名は主に2つあります。
1. Japanese Crane(日本の鶴)
学名の「Grus japonensis」と同じく、日本を代表する鶴という意味です。
2. Red-crowned Crane(赤い冠の鶴)
赤い頭頂部の特徴をそのまま表した名前です。
中国での呼び名
中国語では「丹頂鶴(ダンディンホー)」と呼ばれます。
日本語の「丹頂」と同じ意味です。
鳴き声の特徴
タンチョウの鳴き声は、数キロメートル先まで届くと言われています。
特に朝方、湿原に響くユニゾンコールは、神秘的な雰囲気を醸し出します。
ダンスの意味
求愛ダンスは求愛だけでなく、以下の意味もあります:
- つがいの絆確認:毎年春に踊ることで絆を深める
- 縄張り宣言:周囲への力の誇示
- 若鳥の練習:若鳥が親の真似をして踊ることも
興味深いことに、春の繁殖期、若鳥が親のダンスを真似ようとすると、親はそれを許さず追い払います。
これは子別れを促す行動です。
寿命の記録
飼育下での最長寿命記録は46歳6ヶ月です。
野生では約20-30年とされていますが、個体によってはもっと長生きする可能性があります。
体重の変化
繁殖期のメスは、卵を産む前に通常より体重が増加します。
また、冬季給餌場で十分な餌を得たタンチョウは、春の繁殖期に向けて体重が増加します。
飛行速度と高度

タンチョウの飛行速度は時速約50~60kmです。
渡りをする大陸個体群は、高度1,000m以上を飛ぶこともあります。
日本の県鳥
タンチョウは北海道の「道の鳥」に指定されています(1964年)。
北海道を象徴する鳥として、親しまれています。
よくある質問(FAQ)
Q1. タンチョウとツルの違いは何ですか?
A. タンチョウはツルの一種です。
日本で「鶴」や「渡鶴(わたりづる)」と言えば、通常はタンチョウを指します。日本で観察されるツル類は7種ありますが、国内で繁殖するのはタンチョウのみです。
他のツル類(ナベヅル、マナヅル、ソデグロヅルなど)は冬鳥として渡来します。
Q2. なぜ頭が赤いのですか?

A. 成鳥のタンチョウは、頭頂部に羽毛がなく、赤い皮膚が露出しています。
これは血管が透けて見えるためです。興奮したり威嚇したりすると、血流が増えて赤色がより鮮やかになります。
幼鳥は頭頂部が茶褐色の羽毛で覆われており、成長とともに徐々に赤くなっていきます。
Q3. タンチョウのオスとメスの見分け方は?
A. 外見だけでは見分けるのが非常に難しいです。
一般的にオスの方がやや大きいですが、個体差があり、野外で区別できるほどの差ではありません。
確実な見分け方は鳴き声です:
- オス:「コー」と低く長く鳴く
- メス:「カッカッ」と高く短く鳴く
ユニゾンコールの際、2羽の鳴き声を聞き比べれば判別できます。
Q4. タンチョウは何を食べますか?
A. タンチョウは雑食性で、季節によって様々なものを食べます。
春~秋:
- 小魚、カエル、ザリガニ
- 昆虫類、ミミズ
- 植物の芽や実
冬:
- 凍結しない水辺の小魚
- デントコーン(給餌場)
くちばしで泥や雪をかき分け、餌を探します。
Q5. タンチョウの寿命はどのくらいですか?
A. 野生:約20~30年
飼育下:平均約30年、最長記録46歳6ヶ月
飼育下の方が長生きする傾向にあります。野生では天敵、病気、事故などのリスクがあるためです。
Q6. なぜタンチョウは減ったのですか?
A. 主に2つの原因があります。
1. 乱獲
明治時代、銃の普及により食用や羽毛目的で大量に捕獲されました。
2. 生息地の破壊
湿原の農地開発や森林伐採により、繁殖地と採食地が失われました。
その結果、一時は絶滅したと思われるほど減少しました。
Q7. どうやって復活したのですか?
A. 1924年に北海道で再発見された後、以下の取り組みで復活しました。
保護活動:
- 1935年 天然記念物指定
- 1952年 特別天然記念物指定
- 1960年代~ 冬季給餌の開始(伊藤良孝氏の功績)
- 1987年~ 野鳥保護区の設置(日本野鳥の会)
- 湿原の保全と復元
これらの活動により、わずか十数羽から約1,650羽まで回復しました。
Q8. タンチョウはペットとして飼えますか?
A. いいえ、飼えません。
タンチョウは特別天然記念物であり、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により国内希少野生動植物に指定されています。
捕獲、飼育、譲渡などが法律で禁止されています。
動物園や自然保護センターなどの特別な許可を得た施設のみが飼育できます。
Q9. 鶴の恩返しは実話ですか?
A. 民話であり、実話ではありません。
ただし、山形県南陽市には「金蔵」という人物の体験として伝承されており、関連する地名や史跡が現存しています。
民話は地域の人々の自然観や道徳観を反映した物語であり、「心の真実」を伝えています。
Q10. タンチョウを見に行くにはいつが良いですか?
A. 冬季(11月~3月)が最適です。
特に1月~2月は:
- 給餌場に最も多く集まる(200~300羽)
- 求愛ダンスが見られる
- 雪景色とのコントラストが美しい
早朝(日の出前後)が最も観察しやすく、撮影にも適しています。
まとめ|タンチョウと共に生きる未来へ
タンチョウ(渡鶴)は、日本の自然と文化の象徴です。
その美しい姿は、古くから人々の心を捉え、絵画、文学、民話に描かれてきました。
明治時代の乱獲と開発により一度は絶滅の危機に瀕しましたが、多くの人々の懸命な保護活動により、奇跡的に復活を遂げました。
わずか十数羽から1,650羽まで回復したことは、日本の野生動物保護の大きな成功例です。
しかし、タンチョウはまだ完全に安心できる状態ではありません。
現在の課題:
- 交通事故の増加
- 給餌依存からの脱却
- 遺伝的多様性の確保
- 生息地の分散
これらの課題を解決し、タンチョウが本当の意味で自立して生きていける環境を整えることが、私たちの使命です。
タンチョウの存在は、私たちに何を教えてくれるのでしょうか?
- 自然との共生の大切さ
- 一度失ったものを取り戻すことの困難さ
- 地道な保護活動の重要性
- 次世代へ美しい自然を残す責任
鶴の恩返しの物語が教えてくれるように、恩を忘れず、約束を守り、大切なものを見失わない心が必要です。
タンチョウは、美しいだけではありません。
その存在は、湿原の生態系が健全であることの指標でもあります。
タンチョウが住める環境は、多くの生き物にとっても住みやすい環境なのです。
ぜひ、実際にタンチョウを見に行ってください。
北海道の雪原で求愛ダンスを踊るタンチョウ、岡山の庭園で優雅に佇むタンチョウ。
その姿を目にしたとき、なぜ古の人々がこの鳥を神聖視し、文化の中心に置いたのかが、きっと理解できるでしょう。
タンチョウと共に生きる未来を、私たち一人ひとりの行動で作っていきましょう。
参考文献・出典
本記事は以下の信頼できる情報源を参考に作成しました。
公的機関
- 環境省「タンチョウ」
https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/tancho.html - 文化遺産オンライン「タンチョウ」
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/140167 - 鶴居村公式サイト「タンチョウの生態」
https://www.vill.tsurui.lg.jp/
研究機関・保護団体
- 日本野鳥の会「タンチョウ保護の取り組み」
https://mobile.wbsj.org/activity/conservation/endangered-species/gj_hogo/ - 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ「タンチョウについて」
https://tancho.marimo.jp/tancho.html - 岡山県自然保護センター「タンチョウについて」
https://okayama-shizenhogo-c.jp/tancho
文化・歴史
- Wikipedia「タンチョウ」
https://ja.wikipedia.org/wiki/タンチョウ - Wikipedia「鶴の恩返し」
https://ja.wikipedia.org/wiki/鶴の恩返し - 南陽市「南陽市の民話と伝説」
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kankomidokoro/338 - 岡山後楽園「タンチョウ」
https://okayama-korakuen.jp/midokoro/473.html - Highlighting Japan「ツルにまつわる民話が伝わる里」
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202312/202312_02_jp.html
観察施設
- サントリー愛鳥活動「タンチョウ|日本の鳥百科」
https://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/detail/1341.html - キヤノンバードブランチプロジェクト「タンチョウ」
https://global.canon/ja/environment/bird-branch/photo-gallery/tancho/ - よこはま動物園ズーラシア「タンチョウ」
https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/animal/yamazato/post_55/
関連記事
当サイト「ぽうぽうぽうず」では、他にも野生動物に関する記事を多数掲載しています。